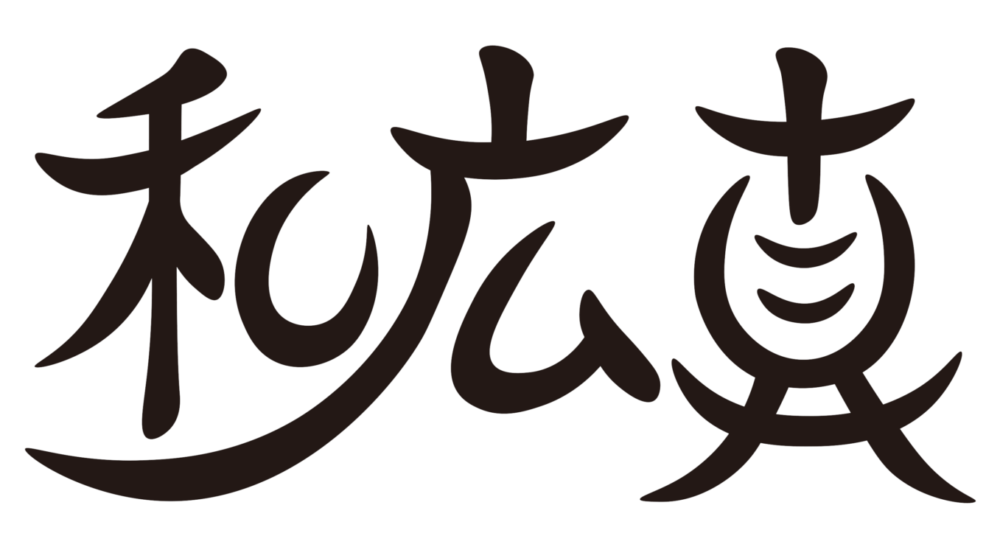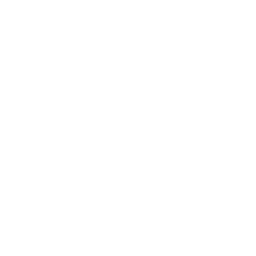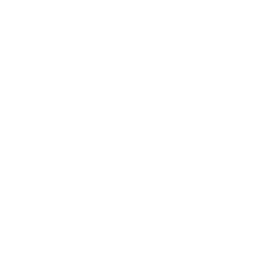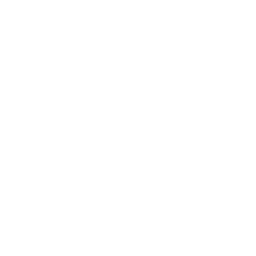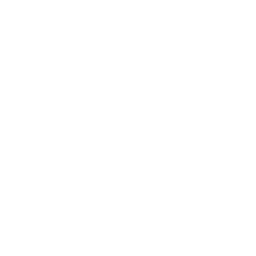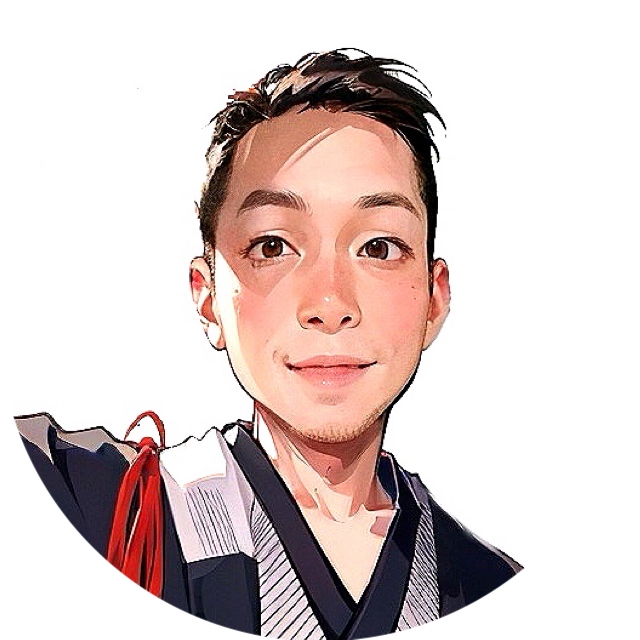
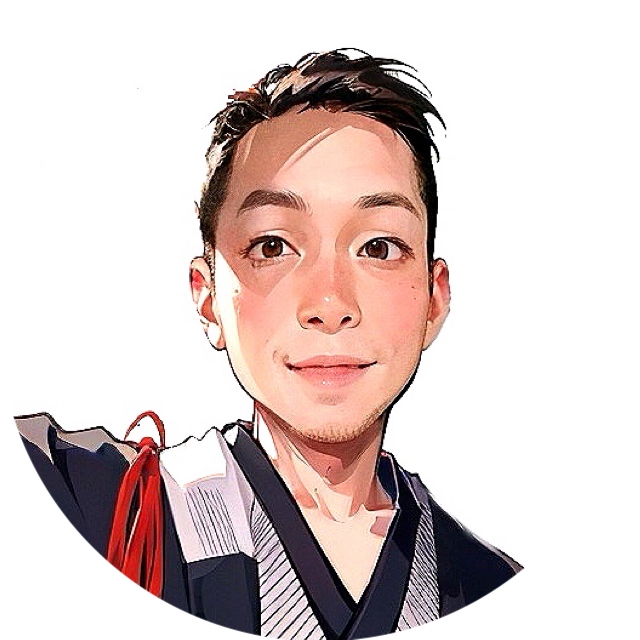
行灯のデザイン装飾「天然木」を施したオリジナルの和風照明18選
はじめまして灯り作家「わひろ」です
和の趣を感じる「天然木」を施した
行灯を集めました。
木の質感や木目の美しさを
活かしたデザインは、灯りとともに
空間に温もりを与えます。
こちらの記事では、
行灯に施した個性的なデザインを紹介。
光と影が生み出す癒しの空間演出とは?
和モダンなインテリアの参考に、
理想のデザインを見つけてください。

障子戸/格子戸




自宅の障子戸(しょうじど)や、近所の格子戸(こうしど)を参考に組んでみました。規則的に並んだ縦の棒に、自由に横の棒(横桟よこざん)を組み合わせると、さまざまな風景を作り出すことができます。
格子状の扉は飛鳥時代、
奈良県の法隆寺金堂(世界遺産)の
板戸(いたど)という建具(木の扉)が
始まりとされています。
江戸の建具師の組子細工によって
扉に美しい装飾が施されました。
現代の街並みにも残されています。
組むときの「縦の棒」と「よこの棒」の
細さや本数で名前を変えています。










京の格子戸/都の横格子


京の格子戸(きょうのこうしど)
直感的に「京」というだけの印象で
桧(ひのき)を組み合わせ
キレイな一枚板の格子を表現しました。
美しく配列された繊細な格子には
風を通し、物を通さず。
古くから悪いものを除ける
縁起の良い文様とされています。


都の横格子(みやこのよこごうし)
6本格子を横にあしらった、デザイン
「6」は調和を表す数字。
そして横に伸びる格子には、
辺りの空間を広くみせます。
この作品は、直感で配列したデザイン
完成してみれば、上品な雰囲気で
ふと「都」という言葉が浮かびました
左が「京の格子戸」
右が「都の横格子」
と言います。










狐窓/木連格子


狐窓(きつねまど)
お寺などの屋根の下に設けられた窓
正方形に組まれた枡(マス)状の窓を
狐窓と呼ぶようです。
その名前と配列をみて
子を育てる狐の姿を想像し組み上げました
強固に配列された
枡状の格子が美しいです。


木連格子(きつれこうし)
お寺などの屋根の下に設けられた窓。
その意味を調べると…
木連/狐格子きつねごうし」とも呼ばれ
木が連なったという意味がなまって
(きつれ▶︎きつね)と呼ばれた説があります。
このような木を連れるという意味をそのまま
木材の配列に表現しました。
木が連なる格子はどちらか
お分かりになりますでしょうか。
左が「狐窓」
右が「木連格子」
と言います。










交わる道縁/川縁


交わる道縁(まじわる みちえにし)
作家一年目。木材を使った2つ目の作品。
道と川の繋がりを表現しました。
人々や生物にとっての道(川)は
「繋がり」と「繁栄」の象徴
交差する縁にそんな願いを込める作品です。


交わる川縁(まじわる かわえにし)
作家一年目。木材を使った3つ目の作品。
川の繋がりを表現しました。
はじまりは何となく木材を3本縦に置き
繋げるように横に木材を配列。
直感を発揮した作品の1つです。
完成してから作品の意味を考えました。
どちらが川でどちらが道に見えますか?
左が「川縁」
右が「道縁」
と言います。










箱根旅の屋/宿の窓
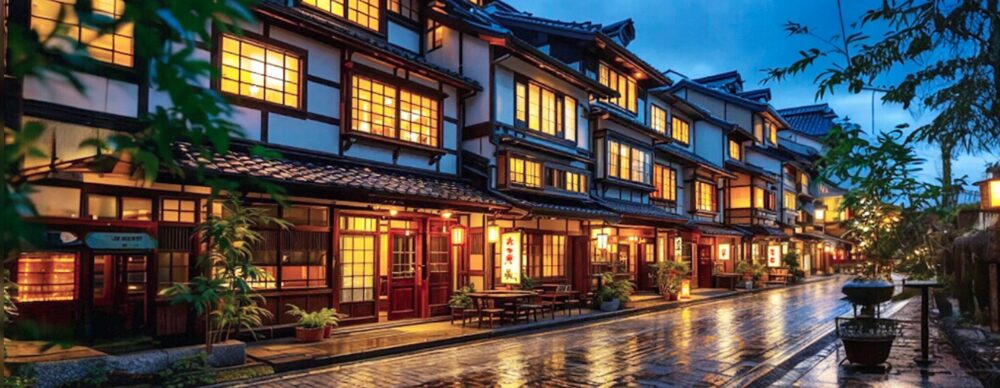
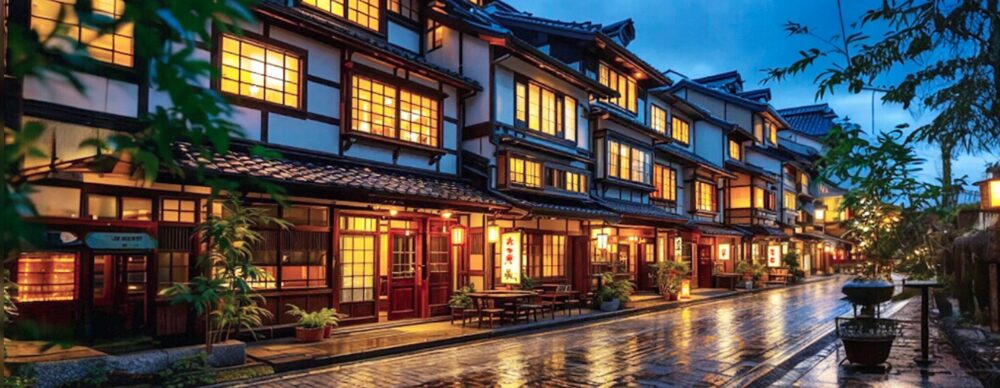
箱根旅の屋(はこねたびのおく)
コロナ禍の時に、ドライブした夜の箱根。
旅館の窓からもれる賑やかな灯りが美しく
「泊まりたい、行きたい」
そんな想いを灯影しました。
ワクワクするノスタルジックな雰囲気
旅館に行った気持ちになるデザインです。


箱根宿の窓(はこねやどのまど)
コロナ禍の時に、ドライブした夜の箱根。
宿の窓からもれる落ち着く灯り。
素朴さが安心できる「民宿」を表現しました
見たものをデザインとして
形にすることを学んだ作品です。
それだけ行きたかった事を実感しました。
左が「箱根旅の屋」
右が「箱根宿の屋」
と言います。










風車 かざぐるま/ふうしゃ


風車(かざぐるま)
中国から平安時代に渡来して
子供の遊び道具になった、かざぐるま
江戸時代を映したドラマで
子供が風車で遊ぶイメージがあります。


風車(ふうしゃ)
エジプト紀元前3600年。
風を動力に他の力に変える風車。
このデザインの灯りがあると
気持ちいい風が家中に流れ
気分が晴れそうです。
この作品のはじまりは、
友人が卍を描こうとして
それを風車と解釈してリメイク
「ふうしゃ」はどっしりと佇み
「かざぐるま」は持ち運びやすく。
そんな違いを表現してみました。
左「ふうしゃ」は風を電力に変え
右「かざぐるま」は風を楽しみにかえます。
変化をしたい時に取り入れてはいかがでしょう










月への階段/朧と霞


月への階段(つきへの かいだん)
地元でみた、海に浮かぶ満月。
波に映る朧げな月光をみて
「月への階段」を想い出しました。
この階段は、月に向かい一段ずつ登る姿に
「叶う希望」と「気分上昇」の
願いが込められています。


朧と霞(おぼろとかすみ)
朧は、夜の霧(きり)
霞は、秋の霧(きり)
自然現象を木材の影で表現しました。
このデザインのはじまりは、
雲をイメージして配列し霞文様に出会い
参考にしました。
霞文様には古くから「永遠」の願いが
込められています。
「霞」と「月への階段」どちらか分かりますか?
場所と木の太さで違いを作ってみました。
左が「朧と霞」
右が「月への階段」
と言います。










部屋繋ぎ/空間繋ぎ


部屋繋ぎ(へやつなぎ)
木材を迷路のような廊下に見立て
部屋を繋いでいく様子。
平安時代の寝殿造(しんでんづくり)を
表現しました。
色々な形の部屋ごとには
想い出が繋がっています。


空間繋ぎ(くうかんつなぎ)
よく行く静岡県の旅館に備えられた
和風な仕切りのデザインを
そのまま、まるっと参考にしました。
部屋繋ぎと似て、空間を繋いでいく。
そんな印象から名前をつけました
どちらが部屋を繋ぐ廊下で、
どちらが空間を区切る様子か
分かりますでしょうか。
左が「部屋繋ぎ」
右が「空間繋ぎ」
と言います。










竹格子




竹格子(たけこうし)
水墨画で描かれた竹を見て閃きました。
太い木材で「節/茎(稈(カン))」を作り
細い木材で「節目」を交互において
堅牢な竹の城門を表現しました。
竹の「頑丈さ」と力強く伸びる姿に「向上」
また竹の花言葉には
「無事」「長寿」があり参考にして
デザインを組んでみました。
白透きの港




白透きの港(しらすきのみなと)
格子窓を民家にみたて、
6本の格子で堤防を構築。
その先に透きとおる白い世界と
静かな港をアシンメトリーに表現。
静岡県〜熱海の海をみて
この場所の江戸時代は
どうなっていたんだろう…
想像をそのままデザインしました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
直感でデザインした作品や
日常の風景をヒントにした作品を
天然木だけをつかって表現しました。
新しいデザインを見つけた時は
更新していきます。
今回ご紹介したデザインを
灯り箱に灯影しませんか?
\ 和モダン空間を手軽につくる /